専門学校の入試では、面接試験が課される場合が多くなっています。面接ではどんなことを聞かれるのでしょう?また、どういった準備をして、どのようなところに気を付ければいいのしょうか?
面接では、志望理由や自身の将来像を具体的に伝えることはもちろん、受け答えのマナーや態度も重視されます。受験生の熱意や人柄を見極めようとしており、第一印象や話し方なども評価されます。
専門学校を目指す高校生の皆さんへ、本記事では面接対策のポイントを整理し、合格を勝ち取るためのヒントを詳しく解説します。
面接対策の手順や準備方法、マナーの基本を押さえることで、当日の緊張をやわらげ、アナタの魅力をより効果的に伝えられるようにしましょう。
目次
専門学校の面接試験の重要性

専門学校の面接は、適性や熱意を直接アピールでき、学校側とのミスマッチを防ぐ重要な場。
「なぜこの分野を学びたいのか」「将来どのように活かしたいのか」熱意や目的意識を深く伝える貴重なチャンスになります。
学校側も受験者が本当に学科内容に合っているかを確認する目的で面接を実施しています。いざ入学してから、思っていた分野と違ったというミスマッチを防ぐためにも、お互いに理解を深めることが肝心です。
面接にどう備える?
本校の入試にも面接試験は課されています。では、アナブキを受験する際、面接試験にどう備えておけばいいのか。アナブキの進活通信「アナ通」に面接試験への備え方が記載してありますので、受験を考えている人は確認しておきましょう!
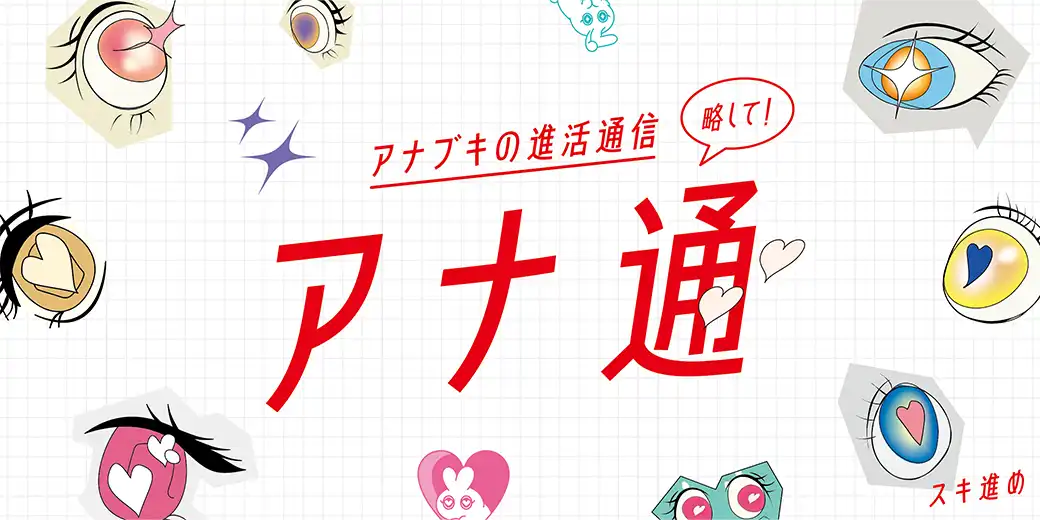
専門学校の面接の形式とは?
専門学校で行われる主な面接形式を理解し、適切な対策を立てましょう。
専門学校の面接は、個人面接から集団面接や討論面接など、それぞれ求められるアピールポイントが異なるため、どの形式で受験するのかをしっかり理解しておくことが大切です。
個人面接であれば、より深く自身の考えや経験を掘り下げて話すことができます。集団面接では、他の受験生と比較されやすい一方で、協調性やコミュニケーション力を大いにアピールするチャンスが得られます。
また、討論面接では与えられたテーマについて意見を交換し合うことで、論理的思考力やリーダーシップ、柔軟性などが評価されます。
個人面接
個人面接は一対一のため、受験生にとってはじっくりと自分の強みや志望理由をアピールできる場となります。面接官との対話の中で、受験生の人となりを深く探ることが可能。
質問も多岐にわたり、志望動機や将来のビジョン、具体的なエピソードなどを詳細に聞かれる場合が多いでしょう。想定される質問への回答をノートにまとめ、話し方の順番を整理しておくことが挙げられます。
緊張しやすい人は、模擬面接などで練習しておきましょう。自分自身を客観視することで、より説得力のある受け答えができるようになります。
集団面接
集団面接は複数の受験生と同時に行われるため、短時間で印象を残さなければいけません。また、他の受験生の答えを聞いた上でどのように受け答えするかも重要になってきます。
この形式では、面接官からの質問に一人ずつ答える「一問一答形式」が主流となっています。他の受験生とのバランスを保ちながら発言する力が求められます。
個人面接と同じように、事前に予想される質問に対して自分ならではの答え方を考えておきましょう。
討論面接
討論面接では、与えられたテーマについて受験生同士が議論を行い、思考力やリーダーシップ、他の受験生との連携力を評価されます。論点を整理しながら、自分の意見を論理的に伝えることが求められます。
アピールするために持論を押し通すだけではなく、周囲の意見を理解しながら話を進める姿勢も大切。専門学校の学習環境では、チームでの課題や実習が多いため、こういった面が重視されることがあります。
自分の意見と他の意見を結びつけることで、議論を発展させる練習をしておくのも効果的です。
面接でよく聞かれる質問と答え方のポイント

専門学校の面接で、よくある質問は志望動機や入学後の目標、高校生活で得たことなどが挙げられます。これらの質問に答える際には、自身の体験や具体例を交えて話すことで説得力を高めることができます。
ただ回答するだけでなく、なぜその答えに至ったのかを話すことで、自分らしさをアピールしましょう。特に、なぜその専門学校を選んだのか、その学科が自分の将来にどうつながるかをきちんと説明することが鍵です。
内容だけでなく、声のトーンや話すスピードにも注意し、落ち着いてしっかりと伝えましょう。
志望動機・志望理由
自分がなぜ学校や学科を選んだのか、背景には何があるのかを明確に伝えましょう。高校時代に興味を持ったある出来事や、特定の授業がきっかけとなっている場合はそのストーリーを盛り込みます。
理由が「就職率が高い」など表面的なものだけではなく、「学びたい技術でどのように社会に貢献したいか」など、具体的に将来像を描けるといいですね。
過去の体験や将来の目標、自分がなぜその分野に惹かれたのかを明示しつつ、専門学校の特色とも絡めてアピールしましょう。
アナブキの受験を考えている人は、アナブキの特色もしっかり理解しておこう!
入学後に学びたいこと・将来の目標
「具体的に何を学びたいか」を話すときは、学校のカリキュラムや実習内容などをよく調べておくことがポイント。自分が興味を持っている分野と学校で学ぶことがどのように将来につながるのかを説明するとよいでしょう。
将来の目標については、職種や業界への具体的なビジョンを語ると説得力が増します。たとえば、どのような資格を取得したいのか、どんな企業で力を発揮したいのかを明らかにしましょう。
単に「~になりたい」という漠然とした夢だけではなく、どのステップを踏んで成長していくのかも併せて話ができるとさらに評価が上がります。入学後の学習計画と将来のビジョンをセットで伝えることが重要です。
高校生活で取り組んだことや学んだこと
部活動や委員会活動、アルバイトなどを通じて得た経験は、面接官が受験生の主体性や協調性をイメージしやすい具体例となります。どんな課題があって、それをどう乗り越えたかをエピソードとして語るのも効果的です。
受賞歴などがあれば、その背景にある努力や工夫も伝えましょう。高校生活のエピソードは、ただ事実を話すのではなく、自分の成長につながったストーリーへとまとめることがコツです。
学んだことを今後の専門学校での学習にどう活かしたいかを具体的に示すと、学校側にとって「この学生はしっかりと目的を持って行動している」と感じてもらいやすくなります。
自分の長所・短所や自己PR
長所だけでなく、短所にもしっかりと目を向けることが面接では重要です。短所を素直に認めつつ、それを克服するための具体的な行動や改善策を示すことで、成長意欲をアピールできます。
例えば、自己PRで自分の強みを「計画性があるところです」のように一言でまとめず、具体的なエピソードと結びつけると説得力が増します。過去に成功した体験や困難を乗り越えたエピソードも活用してみましょう。
長所や短所を挙げる際は、あいまいな表現は避け、学校での学びに直接活かせそうな内容を意識するといいでしょう。たとえば「人前で発言するのが得意」「計画をしっかり立てて実行するのが好き」など、学校生活で活かせるスキルを強調するのが効果的です。
困難を乗り越えた経験やエピソード
これまでにどんな困難に直面し、どうやって乗り越えてきたかは、大学や専門学校が重視するポイントです。単なる失敗談だけでなく、その失敗から何を学んだのかを話すことで、自己成長を示すことができます。
たとえば、部活動での失敗や、人間関係の悩みをどのように解決したのか、そこから得た学びを次の挑戦にどう活かしたのかを語ります。具体的な行動やプロセスが明確であるほど説得力が高まります。
困難を乗り越える過程で協力者がいた場合、その人たちから受けたアドバイスや学びを紹介すると、人間関係力の高さや周りを巻き込む力をアピールできます。失敗から成功へのストーリーを上手に伝えましょう。
逆質問への対応方法

逆質問とは面接官から「最後に何か質問がありますか?」と問いかけられることです。
受験生からの質問は、学校側の理解度や入学意欲を示す絶好のチャンスでもあります。
「授業の進め方」や「卒業後のサポート」など、自分が本当に知りたいことを質問することで、入学意欲と準備の丁寧さが伝わります。逆に、基本的な情報を何も調べていないと、興味や熱意が低く見られるかもしれません。
聞いておきたい内容の例
逆質問でよくあるのは、就職率や資格取得率といった数字に関するものです。これらは学校のパンフレットなどにも載っていますが、入学後のサポート体制など踏み込んだ内容まで尋ねるとよいでしょう。
また、クラスの人数や授業形態についても確認しておくと、自分がどのような環境で学ぶのかイメージしやすくなります。興味がある専攻やゼミ、実習施設の設備の質問なども具体的で有効です。
ただし、やみくもに質問を増やす必要はないので、本当に知りたい情報を絞り込み、面接官が答えやすい質問を準備しておきましょう。
学科や卒業後の進路について
専門学校の場合、企業や業界との連携、インターンシップ制度が充実しているところが魅力なので、学科の特徴や卒業生の進路、業界とのコラボ実績などを尋ねてみるとよいでしょう。
卒業後の進路先としてどのような企業が多いのか、在学中にどんな資格取得が目指せるのかといった点も重要です。こうした質問を通じて、学びを将来につなげる意識が高いことをアピールできます。
入学後の目標がある程度固まっている場合は、それを実現するために学校がどのような支援を行っているかにも触れてみましょう。実習環境や就職サポート、キャリアセンターの体制などを具体的に知ることで、面接官に真剣さが伝わります。
AO入試(総合型選抜)における面接対策

自己アピールや志望理由書との整合性が特に重視される総合型選抜でのポイントを解説します。
AO入試(総合型選抜)では、書類審査や課題レポートなどに加えて面接が実施されることが多く、個性や熱意をより強くアピールできます。一方で、志望理由書との一貫性が取れないとマイナス評価につながりやすいため注意が必要です。
面接では「志望理由書に書いた内容が本当に本人の言葉なのか」を確かめるため、さらに深く質問される場合も。書類に書いたエピソードや将来像を、口頭でも矛盾なく説明できるよう練習しておきましょう。
AO入試(総合型選抜)では面接のテーマが独特な場合もありますが、基本的には自分自身の強みを再度アピールする場であることは変わりません。書類では伝えきれない、やる気や情熱を堂々と示すことが大切です。
志望理由書との一貫性
面接時には志望理由書を基にした質問が頻出します。たとえば「書類に書いた部活動の経験をもう少し詳しく教えてください」といった形で深掘りされることが多いです。
このとき、書類に記載していない内容を盛り込むことは問題ありませんが、書類の内容と真逆の主張になるのは避けましょう。矛盾が生じると「信頼できない受験生」という印象を与える可能性があります。
志望理由書との一貫性を保つためには、あらかじめ文面を読み返し、自分が書いた動機や目標を改めて確認しておくことが重要です。回答の中で補足説明を足す場合も、一貫したストーリーに沿うよう意識して話しましょう。
面接前の準備・練習方法

事前にしっかりと練習を行い、本番での落ち着いた受け答えにつなげましょう。
面接準備では、まず想定される質問のリストアップが基本です。志望動機や自己PR、困難を乗り越えた経験など、よくある質問を中心に自分なりの答えをまとめておくと良いでしょう。
録音や録画を利用して自分の話し方を客観的にチェックする方法もおすすめ。うまく話せたつもりでも、声の大きさやテンポ、表情などに改善の余地がある場合があります。
回答のシミュレーション
リストアップした質問に対して文章を暗記するのではなく、キーワードやポイントを押さえておく程度にしておくのがベター。丸暗記だと想定外の質問に対応できなくなるリスクがあります。
回答の際には、「結論→具体例→まとめ」のように論理の流れを意識すると、面接官にわかりやすく伝わりやすくなります。要点を取りこぼさずに話せるよう、最低限の構成は頭に入れておきましょう。
シミュレーションの中で、自分の話が長すぎたり短すぎたりしないかもチェックしてください。自分がどれくらい簡潔に要点をまとめられるかを意識しながら練習することが大切です。
規定の服装・身だしなみ
専門学校の入試では、指定がある場合は制服やスーツを着用するのが一般的です。清潔感を感じさせる服装や髪型で臨むことが好ましく、派手すぎる装飾は避けるようにしましょう。
服装だけでなく、爪の長さや靴の汚れなど細かい点も印象に直結します。面接官は意外とこうした細部にも目を向けるため、トータルで整っているかをチェックしてください。
自分らしさを大事にしながらも、場にふさわしい身だしなみを心がけることが肝心です。
模擬面接
模擬面接はなるべくやっておきましょう。家族や友人など身近な人に面接官役をお願いするのが効果的です。やりにくい部分や答えづらい質問に気づく良い機会になります。
第三者からフィードバックをもらうことで、自分では意識しづらい癖や言い回しに気づくことができます。表情や姿勢など、自分だけではチェックできない点に関して意見を聞くのは大きなメリットです。
もし可能であれば、学校が主催する面接対策講座に参加するのもおすすめです。いろいろなパターンの質問に対応できるよう備えておけば、本番に落ち着いて挑めるでしょう。
面接当日の流れとマナー

面接当日は余裕を持って会場に到着し、控え室での待ち時間も集中力を保つことが大切です。バタバタと準備をしていると、不安や落ち着かなさが高まり、最初の印象にも影響しやすくなります。
控え室では、大声で話したりスマートフォンを操作したりする態度は避けましょう。周りの受験生や学校スタッフの視線があることを意識し、静かに待機しておくのが望ましいです。
入室や挨拶といった基本的なマナーをしっかりと守ることで、面接官に好印象を与えられます。退室までの一連の流れを頭に入れておくと、想定外のトラブルにも落ち着いて対応できるでしょう。
集合から控え室での過ごし方
集合時間よりも早めに到着するのは基本ですが、あまりに早すぎると余計な緊張を生む場合もあります。適度な時間に到着し、受付を済ませたら控え室で落ち着きましょう。
控え室では、自分が話す内容を最後に確認したり、深呼吸をして緊張をほぐしたりするのがおすすめです。他の受験生と情報交換をするのも良いですが、必要以上に雑談にのめり込まないよう注意が必要です。
待ち時間が長いときは、あらかじめ準備したメモや学校のパンフレットを再確認するなど、面接に関係することに集中すると心が落ち着きます。
入室・着席・退室の手順
まずは3回扉をノックし、「どうぞお入りください」という入室の許可を得てから、はきはきとした声ではっきりと「失礼します」と述べ入室しましょう。相手の目を見ながら45度の角度を意識して「よろしくお願します」と一礼をするのが良いです。
椅子に座る際には、面接官からの指示があるまで立ったままで待機します。着席時も急にドサッと座るのではなく、ゆっくりと腰掛けると落ち着いた印象を与えられます。
退室の際は再度挨拶を忘れずに。「ありがとうございました」と感謝の気持ちを込めて礼をし、扉を静かに閉めるのが基本的なマナーです。
印象を良くする姿勢や言葉遣い
姿勢は背筋を伸ばし、目線はなるべく相手の顔や目を見るようにしましょう。下を向いたままだと、自信がないように見えてしまいます。
言葉遣いは丁寧に、けれど硬くなりすぎないように気をつけてください。相手の質問を聞く際は、うなずきや軽い相づちなどを挟むと、コミュニケーションがスムーズになります。
緊張して早口になりがちな場合は、意識して間をとりながら話すと落ち着きを演出できます。冷静に伝えたいことを整理しながら発言すると、面接官にも好感を持たれやすいです。
面接で落ちる理由とは?失敗を防ぐコツ

面接で不合格になってしまう要因を把握し、事前に対策を練ることが重要です。
面接で落ちてしまう理由として多いのは、志望動機や自己PRがあいまいで、説得力に欠ける場合。自分が専門学校で何を学びたいのか、どのように将来に活かしたいのかが明確になっていないと、面接の姿勢にも影響が出やすくなります。
また、マナー面のトラブルも気をつけましょう。例えば時間に遅れる、身だしなみが整っていないなどの表面的な印象の悪さも評価を下げる要因になります。面接官が最初に感じとる印象は思いのほか大きく合否に反映されるものです。
失敗を防ぐためには、基礎的なマナーの徹底と自己分析による回答準備が欠かせません。自分の強みを再確認し、具体的なエピソードを交えつつ、わかりやすく伝える練習を積むことで自信を持って本番に臨めます。
曖昧な回答や自己理解不足
専門学校では、明確な目的意識を持った学生を求めることが多いため、自分の価値観や将来展望をはっきりさせずにいると評価されにくいです。漠然とした志望理由や曖昧な将来の夢だけでは、面接官に強い印象を与えられません。
実際に質問に答えるときも「なんとなく興味がある」や「友人に勧められたから」だけでは説得力に欠けます。自身の体験や能力を踏まえて、どのように専門学校で成長していきたいかを伝えることで、説得力を高めましょう。
自己分析が不足していると、自分の強みや弱みを問われた際に具体的なエピソードを示せず困ってしまいます。これを避けるためにも、あらかじめ高校生活や私生活での経験を振り返り、自分らしさを言語化しておくことが大切です。
マナー違反・受け答えの態度
面接は自分の人となりをアピールする場所であると同時に、社会人としての基本的な振る舞いを見られる場所でもあります。笑顔や挨拶、礼儀など正しいマナーを身につけると好印象につながります。
例えば、スマートフォンの電源を切っていなかった・マナーモードにしていなかった。面接中に着信音が鳴るだけで評価が左右される場合もあります。また、面接官の話を聞いている最中に落ち着きなく姿勢を変えるなども注意が必要です。
申し訳ない態度や謙虚さを欠く態度もマイナス評価となります。受け答えでは「はい」「いいえ」をはっきり述べつつ、相手への配慮を忘れないようにしましょう。
入試を受ける前にオープンキャンパスに行こう!!
オープンキャンパスに行くことで、面接試験でよく聞かれる質問へのヒントが!
オープンキャンパスに行っている・行っていないで、面接試験での答え方も変わってくる可能性があります。
たくさん参加していると、人とは違った見方で答えることができるかもしれません。志望動機の組み立て方や卒業後について、オープンキャンパスでの体験を交えて、オリジナルな回答ができるかもしれませんよ!
穴吹カレッジ福山校を受験を検討している方は、必ずオープンキャンパスに参加して学校のことをよく知ろう!
オープンキャンパスに参加した後は、例年6月から実施される入試説明会へ参加することを強くお勧めします。入試説明会では、アナブキの入試(筆記試験や面接試験)に関する情報をたくさん得ることができます。
また専門学校に進学を目指す人のための進活情報サイト、通称「アナ通」もチェックして、受験に備えましょう。

まとめ・総括
ここまで解説した内容を総括し、専門学校の面接に臨むうえでの最終的なポイントを振り返ります。
専門学校の面接では、自分が何を学びたいか、将来どのようにその学びを活かしたいかを具体的に示すことが重要です。そのために、事前の自己分析や志望理由の整理は欠かせません。
面接当日は、身だしなみを整え、基本的なマナーを守ったうえで堂々と受け答えをしましょう。緊張は誰もがするものですが、落ち着いて自分の言葉で話せるように練習を重ねておくと安心です。
最終的に大切なのは、面接官に「この学校で学ぶ価値を理解し、自分の将来に活かそうとしている」という熱意をしっかり伝えることです。ここまでお伝えしたポイントを押さえながら、ぜひ面接本番で力を発揮してください。
